阿部静子さん、整理収納アドバイザーの活躍!片付けは自分を好きになる手段?収納のプロが教える片付け術とは!?
整理収納アドバイザー阿部静子さんが教える、見た目も使い勝手も抜群の収納術! 16年間「OH!バンデス」出演など、豊富な経験に基づいた実践的なテクニックで、あなたの暮らしを快適に!
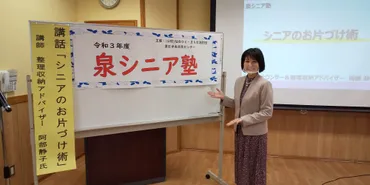
💡 整理収納アドバイザーとして活躍する阿部静子さんの活動内容を紹介
💡 阿部静子さんが提唱する片付けの考え方について解説
💡 SNSで話題の「映える」収納の課題と、阿部静子さんの収納に対する考え方を比較
それでは、阿部静子さんの活動について詳しくご紹介していきましょう。
フリーアナウンサー、整理収納アドバイザーとしての活躍
阿部静子さんはどんな仕事をしているの?
整理収納アドバイザー
阿部静子さんの活動は、まさに片付けを通して人生を変える力を感じますね。
公開日:2022/03/18
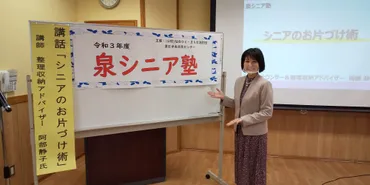
✅ 49歳で整理収納アドバイザーの資格を取得し、仕事に転身した阿部静子さんは、元々は片づけが苦手だったものの、結婚・出産を経て整理収納に興味を持ち、東日本大震災を機にその重要性を改めて認識した。
✅ 資格取得後、カフェやレストランなどで片づけレッスンを始め、市民センターや企業に営業活動を行い、シニア向けの講座を開設した。
✅ シニア向けのお片づけ講座は、阿部さんの得意分野となり、今では企業や市民センターから依頼されることも多く、5年以上続くカルチャーセンターでの「ハッピーお片づけ講座」は、初著書「ハンカチは5枚あればいい」の執筆にも繋がった。
さらに読む ⇒ESSEonline(エッセ オンライン)出典/画像元: https://esse-online.jp/articles/-/1827449歳で整理収納アドバイザーとして活躍されているなんて、本当に素晴らしいですね!。
阿部静子さんは、フリーアナウンサーであり整理収納アドバイザーとして活躍されています。
ブログ「部屋にも自分にも自信がもてる!整理・収納術毎日更新中★」を運営し、著書も多数出版されています。
テレビ、ラジオ、雑誌、新聞など様々なメディアに出演し、講演や司会も多数こなしています。
え、まじ!?49歳で整理収納アドバイザーとか、めっちゃかっこいいやん!
メディア出演と整理収納アドバイザーとしての活動
阿部静子さんはどんな活動をしていますか?
司会、整理収納アドバイザーなど
メディアにも引っ張りだこの阿部静子さん、整理収納アドバイザーとしての活動も多岐に渡り、本当にすごいですね。
公開日:2023/04/07

✅ クローゼットがすでにぎゅうぎゅう詰めで、冬服をしまう前に収納ケースを買おうとするのは、整理をせずに収納品を増やす行動であり、避けなければならない。
✅ 収納品を購入する前に、まず整理をすることで、必要のない収納品を減らし、収納スペースを空けることができる。
✅ 新しい収納品を買う前に整理をすることをルール化することで、収納品そのものがスペースを埋めてしまうことを防ぎ、より効率的な収納を実現できる。
さらに読む ⇒婦人公論.jp|芸能、事件、体験告白……知りたいニュースがここに!出典/画像元: https://fujinkoron.jp/articles/-/8066?page=2整理収納アドバイザーとして活躍する阿部静子さんの言葉には、深い意味と実用的なアドバイスが詰まっていると感じます。
阿部静子さんの主な実績には、ミヤギテレビ「OH!バンデス」の16年間レギュラー出演、結婚披露宴司会800組以上、東北放送「わが町ドまん中!」の4年間レギュラー出演などが挙げられます。
整理収納アドバイザーとして、講演、講座、ワークショップなどを全国各地で開催し、多くの人々の暮らしをサポートされています。
その他、ナレーションなど幅広い活動を行っています。
いやー、整理収納アドバイザーって、めっちゃ稼げるんかな?
SNSで流行する「映える」収納の課題
映え収納、本当に便利?
使いにくくなることも
SNSで流行している「映える」収納は、確かに魅力的ですが、使い勝手や維持管理の面では課題もあるんですね。
公開日:2020/12/22

✅ インスタ映え収納は、収納グッズを先に買うとモノの選別基準がブレてしまい、無理な手放しや詰め込みにつながるため、お片付け初心者にはハードルが高い。
✅ 見た目重視の収納は、中身が見えずアクション数が増えるため、忙しい時やモノの出し入れが頻繁な場合は使いにくく、収納の乱れやモノの存在忘れにつながる可能性がある。
✅ 見せる収納はホコリ対策が必須で、特にキッチン周りの吊り下げ収納は油汚れとホコリが溜まりやすく、こまめな掃除が必要になるため、現実的な維持管理を考慮する必要がある。
さらに読む ⇒たまひよ出典/画像元: https://st.benesse.ne.jp/ikuji/content/?id=93051収納は見た目だけでなく、使いやすさや機能性を重視することが大切だと改めて実感しました。
近年、SNSで流行している映える収納を参考に片付けようとする人が増えています。
しかし、見た目重視の収納は使いにくくなることも多く、家族から使いにくいと指摘されるケースも少なくありません。
えー、収納って見た目重視じゃないと意味ないやん!
阿部静子さんの収納に対する考え方
阿部静子さんの収納術のこだわりは?
見た目と使いやすさ
阿部静子さんの収納に対する考え方は、まさにシンプルで実用的ですね。

✅ 片付けが苦手な人が「映える収納」を目指すと挫折しやすく、自信を失うため、まずは「ラクにできる片づけ」を実践し、成功体験を積むことが重要
✅ 「ラクにできる片づけ」の基本原則として、フタ付きボックスに頼らない、すき間なく収めることにこだわらない、という2つのポイントを挙げている
✅ 片づけは「自分を肯定して好きになる手段」であり、部屋が片付くと気持ちが前向きになり、内面の変化を実感できるようになるため、行動に移し、片づけマインドを育てることが大切
さらに読む ⇒女性自身[光文社女性週刊誌出典/画像元: https://jisin.jp/life/living/2276575/片付けを通して自分を好きになるというのは、とても共感できる考えです。
阿部静子さんは、見た目だけでなく使いやすさを重視した収納方法を提案しています。
片付けで自分を好きになれるって、なんか深いね。
整理収納を通して実現する快適な暮らし
阿部静子さんの活動はどんな影響を与えますか?
整理収納スキル向上
整理収納を通して快適な暮らしを実現できるというのは、素晴らしいですね。

✅ 整理収納アドバイザーの阿部静子さんは、東日本大震災を経験したことをきっかけに、物の大切さと減らすことの重要性を認識し、スッキリとした生活を送るようになった。
✅ 阿部さんは、玄関、キッチン、リビングの片付けのコツを具体的に紹介しており、収納場所を決めたり、必要な物を厳選したりすることで、散らかりやすい場所もスッキリと片付けられるようになるという。
✅ また、阿部さんは災害時の備蓄の大切さを痛感しており、ローリングストックを実践することで、常に備えながら無駄なものを減らす生活を送っている。
さらに読む ⇒ハルメク365|女性誌部数No.1「ハルメク」公式サイト出典/画像元: https://halmek.co.jp/favorite/c/hobby/8654阿部静子さんのような整理収納のプロから具体的なアドバイスをもらえると、片付けがグッと身近に感じられますね。
阿部静子さんの活動を通して、多くの人が整理収納のスキルを学び、快適な暮らしを実現できるようになるでしょう。
家事も仕事も、全部うまくこなせる女って、ホンマに尊敬するわ。
阿部静子さんの活動を通して、整理収納に対する考え方や、快適な暮らしを実現するためのヒントを得ることができました。
💡 整理収納アドバイザーとして活躍する阿部静子さんの活動を紹介
💡 阿部静子さんが提唱する片付けの考え方について解説
💡 SNSで話題の「映える」収納の課題と、阿部静子さんの収納に対する考え方を比較


