避難所運営訓練とは?主体的な防災教育の取り組みから課題まで(避難所運営、防災教育)?主体的な避難所運営と地域防災の強化
東日本大震災の教訓から生まれた、中高生の主体性を育む防災教育の最前線!避難所運営活動やHUG、地域防災訓練などを通して、自らの命を守り、地域を支える人材を育成。車いすユーザーの視点を取り入れた実践的な訓練も紹介。地域防災力向上へのヒントが満載。
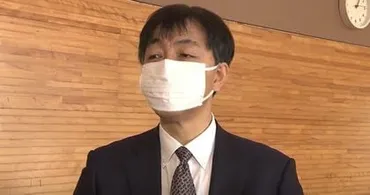
💡 東日本大震災の教訓から、主体的な避難所運営と防災教育の重要性が高まっている。
💡 全国各地で、避難所運営シミュレーションやバリアフリー化に向けた訓練が実施されている。
💡 訓練を通して、避難弱者への対応や地域住民の連携など、様々な課題が浮き彫りになった。
それでは、震災の教訓から生まれた主体的な防災教育の取り組みについて、詳しく見ていきましょう。
震災の教訓と主体的な防災教育の取り組み
南三陸町の中学校、生徒主体避難所運営プログラムとは?
主体性育成を目指す実践的防災教育プログラム
能登半島地震の被災者に向けたメッセージが印象的です。
教訓を活かし、主体的に行動することの大切さを伝えている点が素晴らしいですね。
公開日:2024/01/12
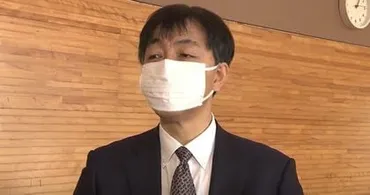
✅ 東日本大震災で避難所運営を経験した宮城県南三陸町の教師が、能登半島地震の被災者に向けて、厳しい状況下でも「生きる気持ちを強く持ち、分け隔てなく助け合う」ことを呼びかけている。
✅ 被災者自身が主体的に考え、行動することの重要性を強調し、過去の経験から「自分が食べるだけでなく、家族や近所の人と分かち合い、共に生きる気持ちを持つこと」を伝えている。
✅ 避難生活の長期化を見据え、地域全体で復旧・復興に向けて主体的に動き出し、人任せにしないことの大切さを訴えている。
さらに読む ⇒プライムオンライン|フジテレビ系局のニュースサイト出典/画像元: https://www.fnn.jp/articles/-/641700?display=full生徒が主体的に避難所運営を行うプログラムは、実践的で非常に興味深いですね。
大人の介入を減らすことで、主体性を育むという点がポイントです。
東日本大震災の経験から防災教育の重要性を痛感した宮城県南三陸町の公立中学校主幹教諭、佐藤公治氏は、生徒が主体的に避難所運営を行う『避難所運営活動』を軸とした実践的なプログラムを開発しました。
この活動は、生徒が40~50代になった状況を想定し、大人の介入を極力避けることで、主体性を育むことを目指しています。
炊き出し訓練やがれき撤去、救命救急などのプログラムを通して、生徒は自らの命を守り、地域を支える人材へと成長することを目指しています。
このプログラムは、学術的にも検証されており、被災地だけでなく、地域防災力の向上に貢献する手法として発信されています。
へー、生徒が避難所運営すんの!?めっちゃ本格的やん!うちも参加したいわー!
全国各地での避難所運営シミュレーションと課題発見
避難所運営を学べるゲーム、HUGってどんな教材?
シミュレーションで、避難所運営を体験できる教材
HUGを活用した防災教育は、ゲーム感覚で楽しみながら避難所運営について学べる良い例ですね。
小学生向けのアレンジも素晴らしいです。

✅ HUGは、避難所の運営を模擬体験できるゲームで、避難者カードを配置し、イベントに対応することで、様々な事情を抱えた避難者への対応を学ぶ。
✅ 静岡県が開発したHUGを基に、浜郷地区まちづくり協議会は小学生向けにアレンジし、小学校の防災教育に組み込んで毎年実施している。
✅ 小学生がHUGを通して防災への興味関心を高め、避難所となる小学校の知識を活かし、将来の防災活動の担い手を育成することを目指している。
さらに読む ⇒浜郷地区まちづくり協議会〈伊勢市〉出典/画像元: https://www.hamamati.com/bousai-top/hug避難所運営ゲームHUGは、地域防災力の向上に貢献する可能性を秘めていますね。
様々な立場の人々が参加できる点も魅力的です。
避難所運営に関する取り組みは、全国各地で展開されています。
静岡県が開発した避難所運営ゲーム(HUG)は、避難所運営をシミュレーション形式で体験し、避難所で起こりうる状況への理解と対応を学ぶための教材です。
研修・学習目標は、児童生徒から自治体職員まで、それぞれの立場に応じたものが設定されており、自主防災組織による住民主体の運営を学ぶ機会も提供しています。
HUGは、2~3時間の所要時間で、定員は教材の数によって柔軟に対応でき、事前準備として、教材や資料の準備、避難所運営マニュアルのチェックが重要です。
また、埼玉県所沢市では、地域防災訓練への車いす利用者の参加を通じて、避難所における課題の確認と解決策の検討が行われました。
いやー、俺、こういうの得意っすよ!俺もHUGやって、みんなを助けたいっすねー!
バリアフリー化の課題と地域での実践的な訓練
避難訓練で重要なのは?要援護者の役割?
地域の実情に応じた環境調整と役割付与。
大槌学園の訓練では、地域住民との連携が図られた点が素晴らしいですね。
中学生が主体的に取り組むことで、地域全体の防災意識が高まることを期待します。
公開日:2019/09/11

✅ 岩手県大槌学園の中学生が、町民も参加して初の避難所運営訓練を実施しました。
✅ 訓練を通して、中学生が避難所運営について学び、地域住民との連携を図りました。
✅ この記事は、避難所運営訓練の様子を伝えています。
さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/graphs/20190911/hpj/00m/040/004000g/20190911hpj00m040033000qバリアフリー化は、避難所運営において非常に重要な課題ですね。
地域の実情に合わせた環境調整と、介助方法の伝達が不可欠であることを再認識しました。
所沢市での取り組みでは、小学校の体育館の入り口やトイレのバリアフリー化といった物理的障壁が確認され、地域の実情に応じた環境調整と介助方法の伝達の必要性が示唆されました。
防災訓練への継続的な参加のためには、要援護者が役割を持つことの重要性も指摘されています。
また、2024年11月には、岩手県大槌町立大槌学園で、中学3年生を中心とした避難所設営・運営訓練が行われ、車いすユーザーを含む被災者役が避難を体験しました。
あらまあ、避難所に車いすの人が来たら、大変じゃわい!でも、みんなで助け合えば大丈夫じゃ!ワッハッハ!
大槌学園での避難所運営訓練の体験と課題
大槌学園の訓練、生徒の課題は?要配慮者への対応?
要配慮者への対応方法の理解不足。
訓練を通して、要配慮者への対応の難しさが浮き彫りになったことは、重要な気づきですね。
事前の学習と情報共有の重要性も理解できます。

✅ 記事は、ある企業の事業戦略と、その戦略に基づいた具体的な取り組みについて記述しています。
✅ 具体的には、組織再編、新技術の導入、顧客関係の強化などが挙げられており、それぞれの施策に対する進捗状況や課題が示されています。
✅ 記事全体を通して、企業の成長に向けた取り組みとその成果、今後の展望について述べられています。
さらに読む ⇒新着記事一覧ブログ出典/画像元: https://blog.canpan.info/nfkouhou/archive/871生徒たちが要配慮者への対応に遠慮してしまう場面があったというのは、課題ですね。
事前の学習不足が原因の一つと考えられます。
大槌学園での訓練では、地震発生のアラート後、生徒たちは避難者の受付、誘導、物資の配布、急病者対応などを行いました。
車いすユーザーを含む被災者役は、移動の困難さや、持病の薬の管理など、要配慮者ならではの課題を体験し、生徒たちが要配慮者への対応に「遠慮」が見られる場面もありました。
訓練後、生徒からは、要配慮者への対応方法が分からなかったという声が上がり、養護教諭は、事前の学習や情報共有の重要性を指摘しました。
町防災対策課は、実際の災害時の規模を想定し、生徒たちに更なる意識改革を促しました。
えー、マジかー。そういうの、事前にしっかり教えてあげないと、意味ないやん!
訓練を通して見えた課題と今後の展望
災害弱者の課題とは?訓練で何が明らかになった?
スロープ、情報共有の課題など、自力解決困難な問題。
辻堂地区の訓練では、車いす利用者の避難訓練が行われたことで、課題が具体的に浮き彫りになったことは、大きな収穫ですね。
公開日:2022/06/03

✅ 辻堂地区で津波避難体験が行われ、住民約300人が参加し、車いす利用者の避難訓練も実施された。
✅ 車いす利用者を想定し、3人1組で階段を上る訓練を行い、参加者からは介助の難しさや役割分担の重要性が語られた。
✅ 訓練では課題も浮き彫りになり、辻堂地区防災協議会会長は、今後の対策を検討していくと述べた。
さらに読む ⇒タウンニュース神奈川県全域・東京多摩地域の地域情報紙出典/画像元: https://www.townnews.co.jp/0601/2022/06/03/628055.html今回の訓練を通して、避難弱者の抱える課題を改めて認識できたことは、大きな収穫ですね。
地域住民の協力を得るための工夫が不可欠です。
今回の訓練を通じて、参加者たちは、自身の想定外の事態や、避難弱者の抱える問題点を改めて認識しました。
車いすユーザーは、スロープの段差や、薬の紛失、情報共有の不足など、具体的な課題を指摘し、自力では解決できない問題も存在すること、そしてそれは高齢者など災害弱者に共通して言えることだと感じました。
今回の訓練は、現実の災害を想定し、より実践的な対応能力を高めるための重要な一歩となりました。
地域住民の協力を得る方法の検討の重要性が改めて示唆されました。
いやー、ほんと大変そうばい!でも、こういう訓練、大事よね!俺も積極的に参加しようかな!
今回の記事を通して、避難所運営の重要性、そして地域全体での防災意識の向上が不可欠であると改めて感じました。
これからも、防災に関する情報の発信を続けていきたいと思います。
💡 東日本大震災の教訓から、主体的な防災教育の重要性が再認識された。
💡 避難所運営シミュレーションやバリアフリー化に向けた訓練が各地で実施。
💡 訓練を通して、避難弱者への対応や地域住民の連携など、様々な課題が明らかになった。


