川原繁人氏ってどんな人?言語学者 川原繁人氏の魅力に迫る!川原繁人氏の多岐にわたる活動を紹介
和光小学校卒業生の川原繁人氏が母校で特別授業! 自身の言葉と海外経験を語り、音声学の魅力を伝えます。 音声学研究を社会に活かす川原氏。言葉の音とイメージの関係を解き明かし、ALS患者向けコミュニケーションツール「マイボイス」開発にも貢献。 慶應義塾大学教授として研究と社会貢献を両立する川原氏の活動に注目! 著書や連絡先も公開。
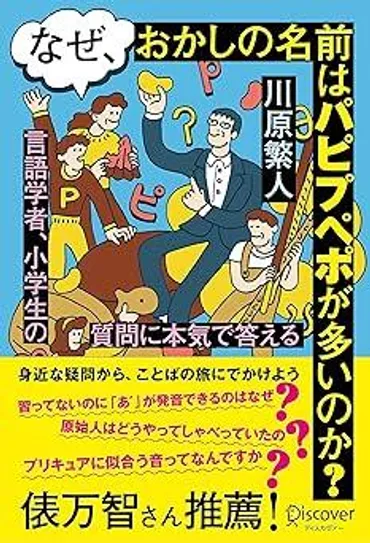
💡 言語学者である川原繁人氏の研究内容や、著書、社会貢献活動について紹介します。
💡 母校である和光小学校での特別授業や、言語学・音声学の面白さを伝える活動に焦点を当てます。
💡 「マイボイス」プロジェクトへの参加など、社会貢献活動についても詳しくご紹介します。
川原繁人氏の多岐にわたる活動について、これから詳しく見ていきましょう。
母校での特別授業:人間性と経験の共有
卒業生が語る!和光小学校教育の影響とは?
人格形成と、言語学への興味を育んだ!
川原繁人氏の言語学への情熱と、子供たちへの教育にかける思いが伝わります。
公開日:2023/10/19
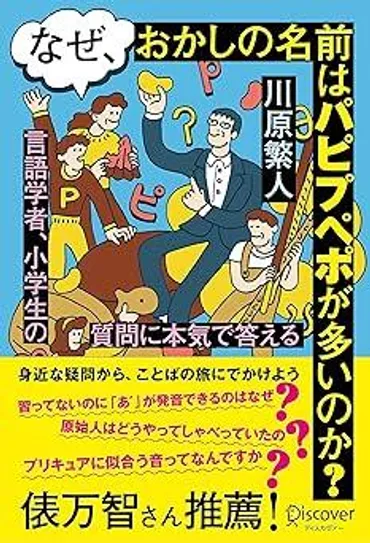
✅ 言語学者の川原繁人氏の著書『なぜ、おかしの名前はパピプペポが多いのか? 言語学者、小学生の質問に本気で答える』は、小学生の素朴な疑問を通して音声学の基礎を解説しています。
✅ お菓子の商品名に「ぱ行」が多い理由として、外来語のイメージや可愛らしさを表現するため、また赤ちゃんが発音しやすい音であるためと解説しています。プリキュアの名前分析も行い、両唇音で始まる名前が多いことを指摘しています。
✅ 本書は、小学生の質問を通して言語学の面白さを伝え、大人も知的好奇心を刺激する内容となっています。親子で一緒に読むことも推奨されています。
さらに読む ⇒AERA dot. (アエラドット) | 時代の主役たちが結集。一捻りした独自記事を提供出典/画像元: https://dot.asahi.com/articles/-/204246?page=1小学生の疑問から言語学の世界を紐解くアプローチが面白いですね。
子供たちが言語学に興味を持つきっかけになりそうです。
和光小学校の卒業生である川原繁人氏は、母校で特別授業を行いました。
自己紹介を通して自身の人間性を伝え、子供たちに海外経験を共有したいという思いがあったからです。
川原氏は、自身の幼稚園時代の写真を紹介し、和光小学校での教育がその後の人格形成に大きな影響を与えたと語りました。
当時の担任の先生たちも参加し、和やかな雰囲気の中で授業は進みました。
この授業は、言語学への興味を抱かせるきっかけとなりました。
えー、なんか真面目な話やね!でも母校で授業とか、ちょっとええやん!先生も楽しそうやったし!
音声学の世界:言葉の音とイメージ
言葉の音とイメージの関係、音象徴について教えて!
言葉の音と形状イメージを探求する研究です。
音声学の奥深さと、言葉の面白さが伝わってきます。
公開日:2024/01/26
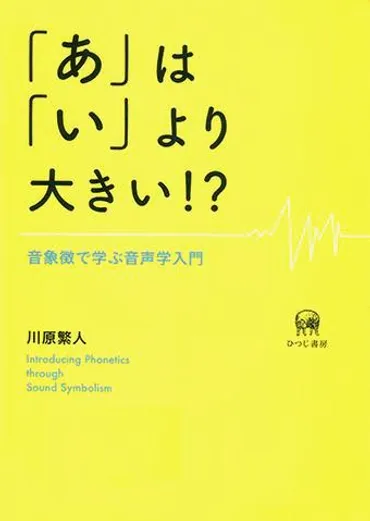
✅ 音声学者の川原繁人氏の著書『「あ」は「い」より大きい !? 』について、音声言語学の視点から、言葉と音の面白い関係性を紹介している。音象徴の研究を通して、言語学、音韻論、心理学など様々な分野との関連性を示している。
✅ 本書では、malumaとtaketeの実験や、名前の魅力度に関する心理学的実験などを紹介し、音のゲシュタルトや阻害音・共鳴音などが人の印象に与える影響について解説している。
✅ 著者は、音声学を専門とし、声帯の振動やベルヌーイ効果など、音声学の基礎的な知識についても触れながら、幅広い読者層に向けて、音声学の面白さを伝えている。
さらに読む ⇒Ueda Nobutaka Formal Site出典/画像元: https://uedanobutaka.com/shigeto-kawahara-part-1-a-is-bigger-than-i-sound-symbols-and-words/音象徴や、音の与える印象について、様々な実験結果を交えて解説しているのが興味深いですね。
言葉の持つ多様な側面を探求しています。
川原氏の専門は音声学であり、言葉の音と語感に関する研究に情熱を注いでいます。
彼は著書の中で、音象徴(言葉の音とイメージの関係)を分かりやすく解説し、音声学の基礎を調音音声学、音響音声学、知覚音声学の三要素に分けて説明しています。
声帯の振動数といった生理学的な側面にも触れ、ゲシュタルト心理学の実験や名前の魅力度に関する心理学実験を紹介し、言葉が持つ形状のイメージを探求しています。
具体的には、男性の名前は阻害音が多く、女性の名前は共鳴音が多いものが好まれる傾向があるなど、興味深い結果を示しています。
へー、言葉って見た目だけじゃないんだなー。なんか、奥深いっすね!
次のページを読む ⇒
慶應義塾大学 川原教授、ALS患者向けツール「マイボイス」開発に貢献!音声学研究を活かし、患者のコミュニケーションを支援。最新版は字幕・スタンプも!連絡先・略歴・著作情報も。

