原晋監督と青学駅伝部:箱根駅伝連覇の裏側にある教育論とは?原晋監督が語る、主体性を育む教育。
箱根駅伝8度制覇の青山学院大学・原晋監督。型にはまらない「原メソッド」で、学生の主体性を育む教育を実践。自由と多様性を重視し、自ら考え行動する力を育む重要性を説く。AI時代に求められるのは、知識だけでなく「学び方」と「軸」を育むこと。指導スタイルの変化や記録的な勝利を振り返りつつ、選手と指導者の関係性、チーム作りについて語る。未来を担う人材育成のヒントがここにある。

💡 原晋監督は、青学陸上部で選手の主体性を重視する指導を行い、自律した人材育成を目指している。
💡 従来の管理教育の問題点を指摘し、変化の激しい現代社会で自ら考え行動できる力の重要性を訴えている。
💡 選手たちの「学び方」を育み、将来社会で活躍できる力を育てる教育の必要性を強調している。
さて、本日は原晋監督の教育論に焦点を当て、その核心に迫っていきましょう。
まずは、この記事で皆様にお伝えしたい3つのポイントをまとめました。
原メソッドと主体性重視の教育
原メソッドの核となるのは?
主体性重視の指導法
原監督のメソッドは、選手の主体性を引き出し、自律を促す教育方法として注目を集めています。

✅ 原監督は、青学陸上部の指導において、従来の管理教育とは異なる「主体性を重んじる」という独自のメソッドを採用している。これは、選手自身に考えさせ、行動させ、自ら「軸」を確立させることで、将来の社会で必要な自立的な思考力と行動力を育むことを目指すものである。
✅ 原監督は、戦後復興期の管理教育が、画一的で主体性のない「金太郎飴集団」を生み出したと指摘し、現代社会では正解が予測しづらい時代であるため、学生自身が自ら考え、答えを掴み取る力が求められると主張する。そのためには、学生自身が「こうなりたい自分」を目指してチャレンジできる文化を育むことが必要だと訴えている。
✅ 原監督は、従来の管理教育では、「言われたことはできるけど、自ら判断したりや思考したりする力が足りない」人が多く、そのような仕事の仕方は将来AIに取って代わられると危惧している。一方で、山本先生は、「感じて、考える力」が子どもたちから奪われている現状を嘆き、原監督のメソッドが、子どもたちに「軸」を作り、人生を力強く歩むための力を与えると期待している。
さらに読む ⇒ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/articles/0744a5e376bde78666134fb24b6cf7ee29284254原監督の指導法は、従来の体育会系のイメージを覆し、画一的な教育の課題を浮き彫りにしています。
選手たちが自ら考え、行動することを促す姿勢は、現代の教育にも示唆を与えています。
青山学院大学陸上競技部監督の原晋氏は、箱根駅伝で8度の優勝を誇る「原メソッド」で知られる。
従来の体育会系とは異なる、選手の主体性を重視した指導法は、陸上界のみならず教育界にも影響を与えている。
原氏は、学生の主体性を育むためには、自由と多様性を重視する考え方と、「型」から生まれる「軸」の重要性を説く。
社会の変化に対応し、自ら考え行動する力を育む教育の必要性を訴え、従来の一斉教授型の管理教育では、AIに取って代わられる可能性を指摘する。
教育界で自律型の教育を実践する山本崇雄氏は、原氏の考えに共感し、学生が自分の軸を作り、社会で応用できる力をつけることの重要性を強調する。
二人とも、現代社会で求められる主体性を育む教育の必要性を訴え、従来の教育方法からの脱却を促している。
へ〜、原監督って、ただ強いチーム作るだけやないんや! 選手のこと、ちゃんと考えてるんやな。なんか、ちょっと見直したわ!
主体性を育む教育の実践
教育で最も大切なことは?
主体的な学びと軸作り
原監督と伊坂氏の対談は、スポーツ指導における教育的視点の重要性を示唆しています。
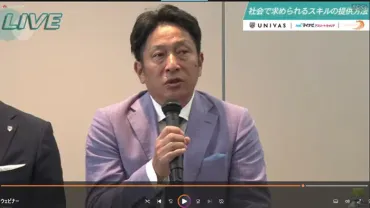
✅ 青山学院大学教授の原晋氏は、箱根駅伝指導を通して選手たちが社会で生かせる計画力やコミュニケーション力を育成することの重要性を訴え、選手自身の主体性を生かした指導法や未来志向のフィードフォワードを取り入れたミーティングの重要性を強調しました。
✅ 立命館学園副総長・立命館大学副学長の伊坂忠夫氏は、探究学習の浸透に伴い、部活動や大学スポーツの指導の在り方も変化する必要性に迫られており、学び方が変われば教え方も変わるため、指導者自身もアップデートする必要性を訴えました。
✅ 原氏は、スポーツ指導を通して選手たちが競技の勝ち負けにこだわるだけではなく、視野を広く持ち、スポーツで培った経験を生かし社会課題を解決することを目指すことの重要性を強調し、スポーツ以外の情報に触れたり、成功体験や失敗体験と向き合ったりする経験を通して、選手たちの言語化する力を育むことの重要性を訴えました。
さらに読む ⇒青学・原監督がスポーツ指導語る「勝てばいい」だけではダメ出典/画像元: https://www.kyobun.co.jp/article/2023101904原監督と山本先生の教育論は、現代社会で求められる自律した人材育成の重要性を説いています。
生徒たちが自ら考え、行動できる力を育むことこそ、教育の真髄であると強調しています。
原氏は「感じて、考える力」を重視し、従来のスマホに頼った行動ではなく、自ら考えて行動することの大切さを訴える。
山本氏は、従来の「敷かれたレールの上を歩く教育」をロープウェイに例え、自ら道を切り開くような教育の重要性を訴えている。
山本先生と原監督は、生徒や選手に「学び方」や「軸」を育てることの重要性を説いています。
山本先生は、ミネルヴァ大学のように、教員は授業での発言時間を制限し、生徒主体型の学びを促進する教育方法を採用しています。
生徒に目標設定をさせ、目標達成のために必要な「学び方」を体験を通して学ばせることで、生徒が自分で勉強できるようになることを目指しています。
一方で、原監督は、初期には君臨型指導で選手に基礎を徹底的に教え込み、その後、徐々に選手に自律を促すように指導方法を変えてきました。
選手との距離を適切に保ち、目標管理ミーティングなどを通して、選手自身が目標を立て、達成するための方法を考え出すことを促しています。
両者は、生徒や選手が主体的に学び、目標を達成していくための「学び方」や「軸」を育てることの重要性を強調しています。
生徒や選手が目標を達成するために必要な能力を育成し、将来社会で活躍できる人材を育てることが、教育の重要な目的であると訴えています。
教員の役割は、単に知識を教えるだけでなく、生徒や選手が学び方を身につけるためのサポートをすること、そして、自立を促すことであるという共通認識が両者から示されています。
いやー、なんかちょっと難しい話やったけど、まぁ、自分で考えろってことやろ?俺もそろそろ、ちゃんと将来のこと考えんとなー。ってか、誰か俺に軸をくれ!
次のページを読む ⇒
箱根駅伝を席巻! 青山学院大学、原晋監督の軌跡を徹底解説。 驚異の成績と、指導スタイルの変遷に迫る! チームを勝利に導く秘訣とは?

